|
|
| |
|
| |
「空き家のままにされてちゃ困るんだよ。放火されちゃ迷惑だから売るか貸すかさせろよ。」 |
| |
このような発言をする人の中には、売ること、貸すことが簡単にできると思っている方も多いのですが、 |
| |
意外とそのハードルは高く、当社のように空き家の所有者に接する機会が多い者としては、 |
| |
「そりゃ、売ることも貸すこともできないのは仕方ないよね。」と思わせる理由がいくつもあります。 |
| |
|
| |
 |
| ■所有者が判断能力に欠ける場合 |
| |
| 所有者が高齢による認知症で判断能力に欠ける場合、 |
| 移転登記時における所有者の意思確認ができないと不動産譲渡はできません。 |
| 具体的には不動産売買の最終段階である移転登記時に、 |
| 自分の氏名、生年月日、空き家の所在地くらいは答えられないと、 |
| 司法書士から意思確認ができないと判断される場合があります。 |
| |
|
 |
| ■所有者が成年後見制度を利用している場合 |
| |
| 成年後見制度を利用している被後見人が所有者の場合、 |
| 売却する前に家庭裁判所から譲渡の許可を得なければなりません。 |
| 成年後見制度は |
| 被後見人の財産を適正に維持することを主たる目的とした制度で、 |
| 大切な財産である自宅を売却するにはそれ相応の理由が必要となり、 |
| 一般的には家庭裁判所の許可は得にくいと言われています。 |
|
 |
| ■所有者がご健在な場合 |
| |
| 長期入院している所有者の中には、 |
| 自宅に戻ることを励みに頑張っている方も多数いらっしゃいます。 |
| 退院の見込みが低いからといって、 |
| 息子や娘が入院中の親に対して自宅の売却を勧めることは、 |
| 決して簡単なことではありません。 |
| |
|
 |
| ■相続で揉めている場合 |
| |
| 所有者が死亡した空き家を売却する場合、 |
| 相続登記を行なった後でなければ売却はできません。 |
| 法定相続人同士が相続の内容で揉めていたり、 |
| 法定相続人の一人が行方不明になっていたりすると |
| 相続登記は行えず、売りに出すことさえできません。 |
| |
|
 |
| ■法定相続人の一人が売却に反対している場合 |
| |
| 通常の場合、息子や娘が法定相続人となります。 |
| 彼らにとってその空き家はふるさとです。 |
| 簡単に手放したり、壊したりしたくない気持ちは十分に理解できます。 |
| 亡くなってさほど時間が経っていなければなおさらです。 |
| |
| |
|
 |
| ■その他の理由 |
| |
| 父親の十三回忌までは自宅で法要を行ないたい。 |
| 先祖代々譲り受けてきた土地だから簡単に手放せない。 |
| 自分が定年退職を迎えたら、戻って住みたい。 |
| など、様々な事情があるようです。 |
| |
| |
|
|
| |
|
| |
このように空き家を売りも貸しもしない所有者には、いたしかたないと思われる事情があります。 |
| |
また、現状のまま維持するという選択しか選ぶことができない人がいます。 |
| |
金銭面だけを考えれば決して得する選択肢ではありません。 |
| |
固定資産税、火災保険、メンテナンス費用、管理費用が毎年発生するだけではなく、 |
| |
土地価格・建物価格は時間の経過とともに下がっていくのですから。 |
| |
|
| |
空き家を現状のまま維持することには限界があります。 |
| |
建物は必ず劣化していきますから、現状維持という選択はいずれ終わりを迎えます。 |
| |
それまでの期間、空き家の所有者やその身内は適正な管理を継続する義務があり、 |
| |
近隣住民は適正な管理がなされている空き家に対しては寛容な気持ちを持つことが必要となります。 |
| |
|
| |
|
|
| 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、 |
| 周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、 |
| 空家等の適切な管理に努めるものとする。 |
|
|
| |
|
| |
このように考えていくと、この「空家等対策の推進に関する特別措置法」第三条は、 |
| |
所有者にとっても近隣住民にとっても重要な条項だということがご理解頂けると思います。 |
| |
次のページからはもう少し詳しくこの第三条について解説したいと思います。 |
| |
|
| |
|
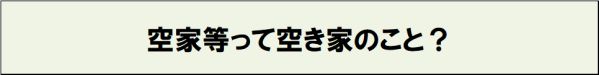 |
| |
|